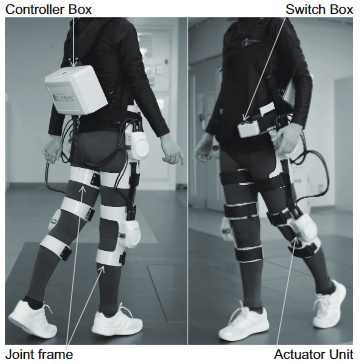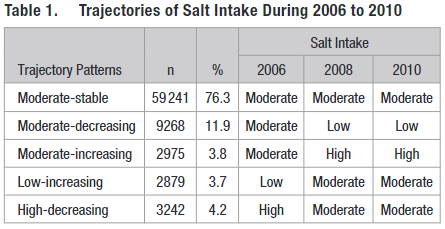元
Five-Year Risk of Stroke after TIA or Minor Ischemic Stroke
2018 5月 フランス
この10年間で脳卒中のリスク要因のおおくが改善され発生率もさがった。
これまで一過性脳虚血発作TIAや軽い脳梗塞のあと1年をこえて長期の再発リスクをフォローした調査はすくなく ひとつの病院施設についてのものしかない。
そこで5年間の再発リスクを多国間の記録から大規模にしらべてみたそうな。
21カ国61施設の2009-2011の患者記録を解析したところ、
次のことがわかった。
・TIAまたは軽い脳梗塞の患者3847人を5年間フォローできた。
・このうち469人(12.9%)が脳卒中や急性冠症候群になった。彼らの50.1%は最初の脳卒中から2-5年後に発症した。
・脳卒中は345人(9.5%)におきて、このうち43.2%は2-5年後に発症した。
・5年間の各死亡率は、トータルで10.6%、心血管疾患2.7%、脳内出血1.1%、大量出血1.5% だった。
・同側の太い血管のアテローム性動脈硬化や心原性脳塞栓が原因のばあい再発リスクが高かった。
TIAや軽い脳梗塞のあと心血管イベントが起きる率は最初の1年間が6.4%で、その後は2-5年間に6.4%だった、
というおはなし。

感想:
きのうのニュースで西城秀樹はサウナが原因で2003に脳梗塞になった みたいな記事がおおかったけど、サウナは脳卒中予防にめっちゃいい。
Neurology誌:サウナが脳卒中予防によいはどの程度かそして2011に再発 さらに食事中に急性心不全で、、ってことだから心原性のそれだったのかな。