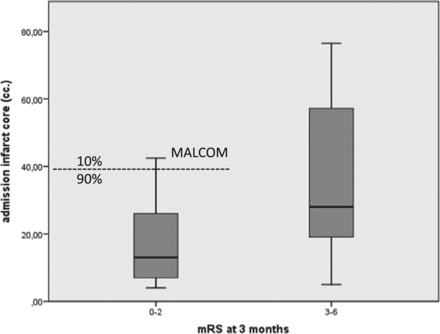元
Unprocessed red meat and processed meat consumption and risk of stroke in the Spanish cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).
2015 9月 スペイン
家畜肉をベーコンやソーセージなどに加工して摂る場合と、未加工な肉として摂る場合とで脳卒中リスクが異なるか調べてみたそうな。
26-69歳の男女41020人を約14年間フォローしたところ、
次のことがわかった。
・この間に脳梗塞531件、脳内出血79件、くも膜下出血42件が起きた。
・加工肉、未加工肉ともに、男女いずれも脳卒中発生率との関連は見られなかった。
・肉をよく摂る人の脳卒中リスクは ほとんど摂らない者に比べ、男性で未加工肉で0.81倍、加工肉0.92倍、女性ではそれぞれ1.21倍、0.81倍だった。
・脳梗塞に限定すると、男性で未加工肉0.80倍、加工肉0.86倍、女性ではそれぞれ1.24倍、0.82倍だった。
家畜肉の摂取は加工、未加工によらず男女ともに脳卒中リスクとの関連は確認できなかった、
というおはなし。
感想:
red meat(赤肉)ってよく出てくるんだけど white meat(白肉)と対になってて、
Red meat-牛肉>羊肉>豚肉>鶏肉もも>鶏肉むね>魚肉-White meat
だいたいこんな感じで境界は資料によりまちまち。
この論文では魚肉と区別するくらいの意味で使っていると考えた。