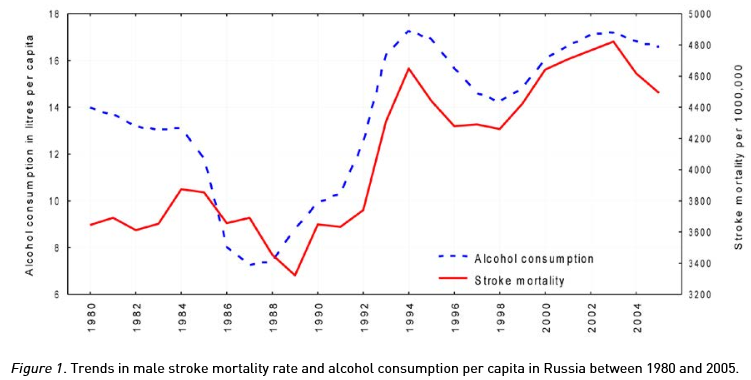元
Effect of dominant hand paralysis on quality of life in patients with subacute stroke.
2014 8月 韓国
利き手が麻痺になった脳卒中患者の生活の質QOLを調べてみたそうな。
亜急性期の脳卒中片麻痺患者を次の2グループに分けた。
*利き手麻痺
*非利き手麻痺
両グループに健康関連QOLアンケートおよび自立度、ウツ度の調査を行い比較した。
次のようになった。
・両グループ間で健康関連QOLに有意な差は見られなかった。
・同様に自立度、ウツ度もあまり差はなかった。
亜急性期に利き手が麻痺している脳卒中患者は、非利き手が麻痺の患者に比べてQOLにさほど違いはなかった、
というおはなし。

感想:
なるほど利き手でないとダメなシーンって 箸、包丁、尻拭き...あまり思いつかない。